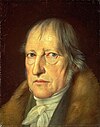哲学概論
哲学・思想 > 哲学概論
『哲学概論』は、哲学という学問分野における基礎的本質的な事項に絞って概説した教科書である。
哲学は、他の学問分野のみならず、各国の統治と政治、各種の思想と宗教はもとより、技術と産業、物流や軍事以外にも、芸術と芸能、エンターテイメントやスポーツとさえ、比較照応の機会を有するとはいえ、少なくともアリストテレスの認識論に遡る、有数の基礎科学についての、科学研究の姿勢を前提とした論述を行う。
既存の研究業績に基き、その師ソクラテスの言行を記録したプラトン、万学の祖として名を馳せアレクサンドロス3世に哲学を教えたアリストテレス、プラトンの証明に反対し人間主義の源流となったアウグスティヌス、神の存在証明の代表者アンセルムス、中世神学の普遍体系の樹立を目指したトマス・アクィナス、経験主義論理学の限界地点を実証したオッカムのウィリアム、更には、オランダからは、デカルト、スピノザ、ライプニッツ、イギリスからは、ロック、バークリー、ヒューム、ドイツからは、カント、ヘーゲル、シューペンハウアー、アメリカ合衆国からは、パース、ジェイムズ、クワインを重視し、他には、ニーチェ、フレーゲ、フッサール、ホワイトヘッド、ラッセル、ウィトゲンシュタイン、ハイデカーを重視する。
ただし、ヒューム、ニーチェ、シェストフ、ハイデカーについては、日本の思想伝統との呼応関係に由来する過大評価を警戒し、必要に応じて著述を制限する。
更に、プラトンの『饗宴』で言及されている事項を含む事柄について述べる。スピノザ、ホワイトヘッド、ツェルメロ、フーコー、パトナムについては、生活様式と境遇を要素とする、他の著名な哲学者との相関に現れた主体性の明確な相違を含めて、当事者の研究内容と他の研究者の研究内容への接続性を含めた言及については、警戒を行い明確に区別する。近年の類例は多いが、煩雑になることから、ここでは明示は行わない。異分野の人員との比較照応に関しては、『ベーオウルフ』とニュートンの主として物理学の研究姿勢についての活動実績を踏まえ、クレオパトラとシャトレの2例を考慮する。
はじめに
[編集]
本書は哲学に関する基礎的な理解を助けることを目的として作成される教科書であり、次のような目標を達成することを狙うものである。
第一に、哲学研究における初歩的な概念、方法、そして理論の概要について示すことを目指しており、重要な哲学者については人物データとして示している。
第二に、哲学における諸領域を概観することを助けるために単元は主題によって区分している。本書は単に初心者に哲学を学ぶ上で最低限必要な知識を付与する入門書でも、専門的な研究活動の上での発展的内容を扱う研究書でもなく、両者を媒介することができる内容となるように試みている。
本書の主題は哲学と定められている。キリスト教、東洋思想におけるイスラム教や仏教、さらに儒教や道教などの思想をほぼ扱っていない。ここで哲学として扱われているのは古代ギリシア哲学に由来し、スコラ哲学の成果を継承し、主に近現代において西欧世界において発展した哲学の研究、さらに現代においてなされた哲学の研究を内容に含んでいる。絶対的な基準ではないが、宗教学や他の学問で扱われる内容を哲学の研究領域として位置づけることを避けた。
ユダヤタルムード、インド思想、中国思想への言及は、同様の理由で極力控えた。
本書の内容は、以下から構成されている。第1章はじめに、第2章哲学の基礎、第3章主要な研究領域、第4章近縁の研究領域、第5章学際的な研究領域、第6章人物列伝。
哲学の基礎
[編集]
哲学(philosophy)とは何かという疑問そのものも哲学的な問題で有り得る。哲学という言葉はギリシア語の「愛する」を意味する接頭辞と「知恵」を意味する名詞が組み合わさった「叡智に対する献身」または「知恵への愛」という合成語として成り立っている。アリストテレスが指摘しているように人間には動かしがたい知的な好奇心があり、哲学では新規の情報を持たずにこのような欲求に応答することが目標とされている。
しかし、それだけではない。メタ哲学(metaphilosophy)では哲学そのものの本性や概念、目標または方法について研究する。メタ哲学では哲学そのものが何であるかを考察し、どのような問題を研究しなければならず、研究のためにどのような方法があるかを明らかにする。これは自明な問題ではなく、古代から現代にかけて哲学の位置づけや方法論は変遷しており、しかも現代においてもメタ哲学には議論の余地が残されている。ここでは哲学の概念、哲学の問題、哲学の方法について概説することで哲学を研究する起点となりうる一般的な理解を促す。
哲学の意義
[編集]哲学の意義について検討する為には、哲学とは何かという問と向き合い、自身と自身が帰属する共同体の語彙を精査し、考察の陳述の健全性を向上する必要がある。少なくとも哲学研究に従事すること及び実践哲学への貢献者として生きることは、博物的な知識や時事的な情報を収集したり情報量を悪用したりすることではない。これは哲学という学問が他の学問とは全く異る水準であっても理解される意義、問題意識に対する能動性を持っていることを示唆している。
ここでは、基礎付け主義と不可知論及び懐疑論の二つの立場から、哲学の意義について異なる見解を確認する。基礎付け主義の哲学で示される哲学の意義とは一般的な理論の構築や整備、特に確実性を堅固にする為の努力に重点を置いている。懐疑論は哲学の意義とはその反省にあり、既存の学説や理論、通念に対する批判的態度が重要視されている。これらは哲学の位置付けをめぐる論争というよりも、哲学の意義に異なる説明が可能であることを示唆している。
基礎付け主義
[編集]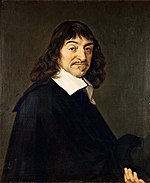
哲学は一般に高度に抽象的な概念を用いながら考察を進める学問である。哲学では世界の根源、人間のあり方、社会の成り立ちについて普遍的な原理や基礎的な概念によって解釈や説明を繰り返し試みてきた。観測される個々の具体的な事象の背景には包括的な原理や単一的な規則性が存在し、それを明らかにすることは哲学者の中心的な関心であった。個々の研究対象を持つ学問を哲学の知見によって総合し、包括的な統一理論を構築する伝統は哲学の指針付けと方向性を顕著に示す考え方の一つであり、基礎付け主義(foundationalism)と呼ばれる。
デカルトは明証性、真理性を疑うことができず、またあらゆる事物の認識がそれに依存するような原理を追及する研究を哲学と見なした。その成果のひとつが「私は考える、ゆえに私はある」として知られるデカルトの命題であり、あらゆる真理の認識の起点としての推論する自我を基礎付ける試みであった。デカルトは少しでも疑いの余地があるものを思考の論拠から排除し、感覚的な経験も数学的な前提も哲学の基礎付けから退けた。そして最後には残った確実な思考の起点とは、そのように真理を求めてあらゆるものを疑う自分自身の自我であると考えたのである。
デカルトの哲学的な態度は、実証的社会転換(positive social change)の旗印であるコントなどによって定式化された社会実証主義(sosial positivism)にも認めることが可能である。実証主義(positivism)は確実に正しい知識とは経験的に観察することができるものに限定されると主張している。ベンサムは、社会において最大多数の最大幸福を実現することを道徳や立法の規範と定めた功利主義の原理を提唱しているが、これは功利を重視した倫理学における一つの基礎付け主義の立場として捉えることができる。
また、ラッセルやウィトゲンシュタインによって示された論理実証主義(logical positivism)はより厳格な基礎を前提としており、哲学における問題のほとんどが生活上の要素との関連を安定的に維持しつつも論理的に無意味であり、概念や言語表現の明確化や経験科学への助力だけが哲学の役割であると論じた。論理実証主義の一人であるエイヤーは検証原理の概念を提唱し、定義によって真であるかどうか、また検証可能であるかどうかによって、それが哲学的な問題であるかどうかを検証することが可能となる原理を示している。これは基礎付け主義においても特に論理的な妥当性を重要視する立場であり、それとは異なる基礎付け主義としては特定の基準を倫理的な問題を評価する根拠として位置付ける立場もある。
不可知論と懐疑論
[編集]少なくとも、キリスト教の成立を追い風としたエピクロスの哲学体系に到達する以前の、キケロとセネカの頃に、外在する知識と存在を根幹から疑問視しし、その不可知を本体とする姿勢の研究が活発に行われた。その研究体系の前期の本体を不可知論(agnosticism)と称する。その不可知論から発展した立場が懐疑論(scepticism)と呼ばれる。哲学は基本的に具体的もしくは個別的偶有的な対象について研究することは無く、既存の思想に対してそれを問題視し、また時には常識から離れて物事を解釈を試みる場合もある。共同体的、社会的、文化的、政治的に、正当であると評価されている考え方であっても、また常識的に疑うことが極めて困難と思える基礎的な信念すらも、哲学を研究する為には批判的な態度を採ることがある。
哲学における懐疑論に対して反哲学的な批判を展開した議論として、プラトンは著作の中でソクラテスに対するカリクレスの主張を紹介している。彼は哲学というものが「必要以上にそれにかかずらっていると人間を破滅させてしまうことになる」と主張している。カリクレスによれば、哲学に没頭している間に人間は国家社会の法律にうとくなり、交渉のための弁論の経験も不足するために非常識を曝し、良い素質を持っていても人間を悪い方向に誘う結果となることを主張する。
ソクラテスはそもそも人間の善悪の基準を問い直すことでカリクレスに応答しており、必ずしも正しさとは自明だとは限らないと反論する。ソクラテスの見解では国家の法律や弁論に習熟したとしても本当の正義を理解しているとは限らず、哲学によってのみ真の正義を理解することが可能となると述べている。当時の古代ギリシアの社会的通念を反映した議論を展開するカリクレスに対して、哲学者としてのソクラテスの反論は哲学の懐疑的な性格を示唆している。ソクラテスは社会の中での常識としての正義を哲学的な思索を通じて改めて根本的に問い直すことを試みている。懐疑論の態度は特定の哲学者の学説にも向けられうる。
論理実証主義による哲学の基礎付けに対して反実証主義の哲学が提起されている。生の哲学者ショーペンハウアーやディルタイなどは実証的な研究にそぐわない人間の生を見出しており、フッサールは直観によって得られる経験を記述、吟味することによってある事象を明らかにする現象学(phanomenologie)を哲学の研究に位置づけた。基礎付け主義に対する重要な批判を展開したローティはデカルト以後の近代哲学が知識の妥当性を基礎付けるため哲学であったことを批判する。ローティはプラグマティズムの立場から哲学を社会的実践の一環として捉えることにより、基礎付け主義から哲学を解放することを主張している。
ドイツ観念論とイギリス経験論
[編集]ドイツ人の哲学についての姿勢のほぼ全ては、その哲学が属する人種と民族の思想風土に依存せずに、哲学の研究業績等が、皆、観念的であるというものである。
それに対して、イギリス人の真理と本質の実在する源泉は、プラトンのイデア論やグリーンの理想主義ではなく、イギリス人が共通して具有している、歴史的な信頼性の上に成り立つ経験であり、しかも、他ではないというものである。
全力で全体主義を維持するのがフランス人であり、パスカル以降も多様な哲学思想を生み出し続けている。
更には、ドイツの隣国、ポーランドでは、現代哲学の啓蒙主義に反対し、ポーランド論理学派を樹立している。
他者に対する留保を当然前提とする理論の一部は、観念論なり記号論なりとして、厳しい批判に晒されることがある。
それらを調停する意見の中でも、最も高い信頼性を獲得しているのは、ライプニッツの哲学体系であり、中世神学でも現代行為論でも同様に高い妥当性を示している。ライプニッツ哲学の普及に先立ち、いち早くラッセルがその指摘を行っている。
唯物論と唯心論
[編集]全ての事物が物質であるなら、人間の意識等も物質に還元されると考える。このような問いは、心身問題として、多様な思考体系を生んでいる。
唯一絶対の支配的な原理を物と見るのか心と見るのかでは、根底的かつ決定的な相違が存在するに違いないが、両者の定式化や調停は依然として完了してはいない。
有神論と無神論
[編集]神学的な前提として、このようなことが言える。唯物論(と唯心論)を無神論と結びつける者もいる。ただし、無神論ならば唯物論とは言えない。人格神論が有神論の全てではないからである。有神論から人格神論を除いた残りが理神論であるとも言えない。トマスアクィナスのように、機械論と生気論の関係を、神に当て嵌める考えを否定する研究者も多い。
無神論の主張を要約すれば、以下のように言えるだろう。「ただ1つ言えるのは、宇宙を創造されたのは神ではない。宇宙に創造主は存在しない。無から何かを作ることは不可能だからだ。この宇宙は今も昔も、変わらない無限なのである。」
哲学の問題
[編集]哲学の議論において取り上げられる問題は特定の主題や対象によって制限されない特徴がある。哲学は概念的な思索が対象とすることが可能なあらゆる事柄を問題としてきた。またどれが哲学の問題であるかどうかを判断する基準は哲学者の立場によって異なってくる。ここでは便宜的に規範的問題と客観的問題に哲学の諸問題を区別する。規範的問題、または道徳的、倫理的な問題とは「どうすべきか」、「何でなければならないか」、「何が望ましいのか」というような疑問を問題としている。また客観的問題とは「どうあるのか」、「何であるのか」、「何が事実であるのか」というような疑問を想定した問題である。この二つの問題は信仰と理性に対応する基本的に混合することができない問題であり、オッカムによって明確に区別されるようになった。ここでは二つの問題の基本的な性質について個別に概説する。
規範的問題
[編集]明晰判明知の異なる人間の生活の細分化と進展、人類の組織体制の細分化と進展、行動と言語的要素の細分化と進展以外にも、規範についての問題は存在している。
客観的問題
[編集]
客観的実在(Objectivity)の問題は、民族と個人を超えて、人類に共通の課題を示している。人類の完全性(complement)は、網羅的な完全性を意味しない。
この意味での客観性の問題に取り組んだ哲学者は数多く、その回答の多くが、解釈者に対する回答のインストールと正当化を期待する性質のものではない。ちんどん屋や噺家との相互独立性は、人類が擁する各職能の完全性を視野に入れたものである。認識論の水準での複数の中核的な同一性原理は、論理的言語的分析とも呼応関係を顕著に示す哲学の業績である。
日本語圏では、物質(または物(もの))の問題が特徴的な役割を演じている。物体の普遍的な学説の提起者といえばホッブズだが、現存の4大公害問題との類比関係が存在し、政府の責任問題にも発展した。
哲学の方法
[編集]哲学において一般的に承認された方法論が確立されているとは言いがたい。その背景には哲学のあり方や問題設定の形式に起因する方法論的な議論があるためである。つまり哲学を研究する上では特定の方法論に頼らずに、問題に対する着目や問題の解釈の仕方、議論で使用する概念の分析と応用、演繹や帰納を用いた論理的な推論の方法、そして結論の検証と問題の解決まで及ぶ創意工夫が求められる。「そもそもその問題は解決が可能であるのか」、「その議論の前提は明確化されているのか」、「その議論において見落とされた要因はないのか」などを総合的に考慮することが哲学を研究する上で必要となる。ここでは特に、問題の設定、概念の分析、そして推論の検証に関する基本的な哲学的思考の手続きについて概説していく。
問題の設定
[編集]統治問題に対する統治者の理性的な反省が存立した地平で、神話が隆盛し、その余波についての反省を踏まえて展開した、プラトンの対話篇の本質的な合意箇所の一つである。ともすれば現代では、性愛と愛欲との予断に埋もれてしまい勝ちな、論理学成立以前の、単射や直示的定義を超えた、非法則的でコロニアルな愛である。プラトンは、善美によって導かれた、全体の経営と分割と再配列の正義と節制を尊重する。
近縁の過去の問題は、ヘシオドスとホメロスに代表される、顕著な先例とは距離を取る、ソロンの潮流を汲むプラトンのオーセンティックな活動の同一性については、詩と歴史との並行関係が指摘されている。数々の「プロトレプティコス」によって証言されるその陰影は、オルガノン樹立に先行する記念碑的著作と相補的なアリストテレスの著作群によって積極的かつ能動的に研究動向を指針付けている。
プラトンに至って開花した問題設定は、今日の基本姿勢と大きくは乖離することなく展開している。ヘレネスとプラグマティストによって指摘された、その指針策定についての問題は、呼応関係を示している。
概念の分析
[編集]事実主義的な合意に抵抗し、著された対話篇は、当初のランガージュの帰趨を超越し、ギリシャ人が獲得したギリシャ型の論理に到達する。プラトンによる、40に迫る主要な主題と現実的な選抜が、各研究者の指針との照応を許し、同様に、論理的言語的分析についても、徹底的な反省を視野に入れた建設的かつ肯定的な姿勢を示している。
対話篇の編纂は語彙の変動と時を同じくしていた。ロゴスに象徴されるストイケイオンの発見と継承発展は、人類が獲得した歴史である。ヘロドトスとアレクサンドロス3世が象徴する人類の共同体の経営負荷の変動は今後も人類の課題との並行関係を有するに違いない。
推論の検証
[編集]2者以上の対話の成立は、必ずしも、不動のランガージュを意味しない。既存論理学の範囲での検証が無意味とは言い切れない。推論の検証は、既存論理学と同等の範囲でのみ成り立つとは限らず、実証主義的な範囲での確認作業も過去に幾度も試みられている。
主要な研究領域
[編集]認識論
[編集]知識
[編集]古代ギリシア以来の知識論では、主要な概念は、包括的な完全性を最大限内在している。主要な概念を原子的な要素とする知識論は、素朴かつ多様な資料を中間的な要素として成り立っている。
知覚
[編集]明晰な形で知覚することは、人生のシーケンシャルなディビジョンを特徴付ける。象徴的な知覚の解明に対する要求は、多様な研究業績を生んでいる。
認識
[編集]抽象的かつ言語的な要素を、知覚と類する体裁で獲得する過程が認識であると言える。その認識相互の関連性は、それ以上の認識にも通じている。
認知
[編集]各自の主体的な認識の限度を超えて、諸集団の認知についての学際領域が存在している。科学哲学の不整合を背景とした、哲学を含む諸科学の学際領域である認知科学である。認知科学における認知は、哲学以外の領域における力と情報の再配列を念頭に置く概念的な要素である。
形而上学
[編集]T・M・ノックスがコリングウッドの研究で明らかにしたように、形而上学的生物学を形而上学的神学と同一視すると、その一つは無生物形而上学となる。形而下の明確な存在、対象、事象を超えて、人間が考察し理論化し知識や認識能力の拡充として認めることが可能な、形而下の抽象的な存在、対象、事象が検討可能である。コリングウッドは、キリスト教神学での感受性と知解作用により、唯一の行為者としての神への言及を正当化している。
プラトンが述べた、記憶の覚醒とも呼べる、産まれて来る以前のことについての研究の強力な勧めは、人類の活動一切の始源としての経営であり、その意味で理解することが可能である。プラトンの主著『国家』の中でも特に10巻で述べられる詩人追放論と称される絵画批判が分岐する明晰さの追求の途は、アリストテレスの主著『形而上学』でそのように述べられている。数学研究の応用的な領域でもある、厳密学や、数学についての還元主義である論理主義は、第一原因への言及等としてその源流の姿を伝えている。微積分の時代は背後状況としての教養の普及であり、ロゴスの集約としての表情を有している。実存主義者カール・ヤスパースは、包摂的かつ超越的な暗号として、歴史上の枢要時代と実存を解明する。
『聖書』は、ノアの名を借りて、神の創造とディアスポラの出来事を深刻な契機として記述している。現在の地球環境と人類の存在容態と各種の活動についても、創造と破滅についての理解が応用領域として存在している。思考の歴史として凡ゆる歴史を評価し考察するコリングウッドは、歴史の間隙から覗き見られる、死、頽落、戦争の深奥に、厳然としている推移の絶対的な存在を痛烈に描写している。
存在
[編集]経験論者は、世界内存在が謬見であることを主張し実証したが、存在一般の解明作業は依然として進展する余地を持つ。例えば、この世界の物資的な存在は、本当に単なる存在の普遍的な存在容態であるのかは、依然として示されてはいない。
自己
[編集]数多くの論者によってより良く理解されている事柄であるが、めいめいの自意識や生命体が、自分自身を識別し認知している状況で、その固有の自己を、期待に適合するかたちで、正当化することができない。それは、単なる物体がそれぞれ異なる存在容態であることとは異なるという予断が多いと同時に、そのような単なる物体に埋もれるかのように潜在してしまう。
人間の各員が期待し理想とする状況の解明や実践は、そこまでは実現していない。そのような過渡的な状況での各員の識別は不十分な状態に留まっている。
相互評価を重視する必要性がそもそも高くはなく、各員の主体的な決定を尊重することなどを踏まえると、不徹底が存在することは、容易に想像できる。
一大体系としての問い
[編集]中世には、国家全体で教育された自然に対する「沈黙」は、17世紀にはフランス科学アカデミーによって、中世の「諦念」の彼方を探求する途として指針付けられた。
中世の論理学によって生成した神の存在証明は、J・S・ミルによって、単なる高座からの批判に晒された。
神学
[編集]古代におけるアルケーの探求は、アレテイア探求の途の一端にもなる。一人称などの、具体的な現実を強力に克服することを伴うことがあり得る。そのような途についての配慮は、アリストテレスの『形而上学』にも、その表れを認めることができる。
自然哲学
[編集]近世の自然哲学の旗印の下、懐疑的な認識の途を再度吟味する学的研究がなされた。
科学哲学
[編集]現在では文転に代表される進学の動向としても存在する科学哲学の途がある。
認知科学
[編集]鈍化した自然科学による牽引を疑問視し、従来の哲学と諸科学の連携を重視することで発展した学際領域の一つが認知科学である。
近縁の研究領域
[編集]論理学
[編集]論理学は、論理の審問を行い、論理の普遍的な究明活動を目指す学問である。
論理
[編集]論理、論理の研究、論理学の存立、ディアスポラの論理と、それに拮抗すると見られる論理を偽装ないし誤認した対象並びに対象の要素の包括的かつ徹底的な研究が求められ、その経緯を伴いつつ、現在の研究動向の客観的な安定感の推移の存立を課題として残していると(も)見られる。 研究動向の客観的な安定感についての省察、再評価、価値と魅力、誘引の発展的かつ機能的な構造の解明作業の表象に対する、具体的かつ建設的な指摘が各専門的な人員の有用性のアピール等についての反省を踏まえて展開することを、条件次第では、念頭に置き考慮する。 尚、国家間の論理にまつわる相違、そして、言語間の論理にまつわる相違、それも具体的な相違が、各種の資料に対する影響力を有している。例えば、2023年には人口世界一となったインド共和国の外務大臣スブラマニヤム・ジャイシャンカルの著書『インド外交の流儀』は、よりプラクティカルな意味での論理を踏まえて、インドの論理に言及している。
排中律、誤謬、真理値もしくは論理値、二重否定、二重否定律、背理法、三段論法等の知識、理解、運用の能力、そして、それらについての、言い換えると、既存論理学についての認識が、広く言語運用と言語的活動にとっての接続性を有し、合理化や効率化といった有益性を持つ。 哲学では、歴史的な来歴を辿ると、逆説的で楽観的な吟遊詩人と扇情的なだけのソフィストによって公知のものとなった一定の類似性を認められる活動に対しての反対が、プラトンを代表とした2400年以上の伝統として、ロゴス・言語についての、真理観が厳然と存在している。
詰まり、哲学では、論理学者による論理の審問であってもその破壊能力を危険視し警戒する。その上で、哲学者たちの主体的な論理観に基き論理と言語を認め、言語観と言語の研究へも応用する。國分功一郎の中動態の研究もこれに相当する。1の5乗根が1であることと同じで、有限の存在としての人間が、寿命の限界を2倍にできないように、人生の結論の種類や強度を2倍にできないことを、フーコーが指摘した。
排中律
[編集]現実、試行、物理理論、そして亦、このようなことの先行研究が、同様の帰結に対しての情報を提供している場合、多少なりとも論理学的な案件が留意の対象であるとしても、それ以上の状況の進展が存在しない場合に基く。 論理学における論理学者の為の配慮と留保が、論理学者による論理学者の為の論理学の活用行為を誘発していることである場合にも、論理学者の私益の追求であっても、主体的かつ能動的な範囲で構成された理論が矛盾している場合であり、それに留まっていることが自明の理でありかつ逆理であり、その上で更に私益の追求であることが別の観点からも問題であることがある。
背理法
[編集]背理法は誤謬の一種である。背理法は、或る仮定が誤りであることに基いて、仮定が誤りであり、その結果として、そもそもの仮定の逆・裏・対偶の正しさを証明しようとする誤謬である。
推論
[編集]論理学の研究の過程で、推論が生じる。推論によって生じる支障を積極的に肯定し、論理の審問を重視するなら、状況次第では、多様な苦情を生じる。そのような状況を無視して、論理学の研究の都合を押し付けることはできない。
矛盾
[編集]論理学者の活動が必ず矛盾しないという保証が存在していない。論理学では、矛盾を、肯定ないし否定、もしくは、真ないし偽の観点から、構造上の必然性に基き、定義しようとしている。実生活では、それ以上の多様性を背景にした、欺瞞的な言い方を含めて、学術的な用語とは大なり小なりの相違を生じている。
倫理学
[編集]倫理学は、共同体における規範・規則・原理などの倫理的な事象を研究する学問である。道徳哲学、道徳学とも呼ばれ、哲学の一分野と見做されることがある。研究領域が有する客観的性質によって推移することもあるが、哲学者と倫理学者の主体性により今後の関係性が変動することは大いに有り得る。
哲学は、倫理学の主体的な拡充と牽引を意味しないという特徴を持つ。実践哲学とも称される倫理学は、根底に横たわる政治構造の問題により、実践哲学とも称される哲学の原義との本質的な対立へと発展するという課題がある。哲学と倫理学の共同研究には、幾つかの問題が必然的に生じる。その一つが比較哲学の問題である。比較哲学については、比較が単に有する性質が顕著に感受され、哲学の本質は全く見えて来ないという状態に堕してしまうことが、懸念される。
メタ倫理
[編集]規範倫理
[編集]美学
[編集]美学は、規範的な美の本質や原理、形式を究明する学問である。その学問は、美醜の問題と向き合いそれを乗り越える姿勢を尊重し、美の追求を理想とした学術的な審問により、美の問題と向き合う。研究対象には、規範的な美の偶有性を獲得した形態としての芸術の研究を含める。古くは審美学とも称した。
美学体系についての主体的な決定と美学体系の立脚と正当化については、ライプニッツよりも後に生まれたヒュームの研究動向の多様性とヒュームにのしかかった本質問題のイングランド本土での帰趨が関係している。学的研究領域の規範の研究への拡張は、美学の創始とも密接に関わり合っている。
美学者佐々木健一の研究姿勢についても、自由が介在する余地を視野に入れている。この事に関して、芸術家の自由の問題がある。セザンヌの例はあまりにも有名である。普仏戦争を戦わずに済ませ、絵を描いていた。新しくはハイデカーによって論じられた常識的かつ否定的な芸術論がある。芸術家各位の生誕が悲劇であり、芸術の本質が詩であること。歴史上の記念碑的な詩の来歴には、改竄を含む隠蔽があったこと。そして、ジルソンが引用したシラーの『芸術家』の一節が痛烈に否定している本質がある。
ウィトゲンシュタインの主著には、「倫理と美は一つである。」という節がある。プラトンの対話篇に始まる基幹的な伝統であり、規範理論についての正当化の姿勢としては最も顕著なものである。
芸術学
[編集]芸術学は、偶有性を獲得した諸芸術についての個別の実証主義的な研究の総称である。諸芸術家の技術知を超越した領域を擁する。
規範的な学問追求を本分とするからには、文字言語と音声言語による研究が中核になるが、キリスト教成立以降の伝統として、図像の研究を擁している。その一部は、図像学及び図像解釈学として形式化されている。図像学は、宗教的な背景に基いた、実践的な要素の原動力としてのアトリビュートと、一定の様式を示す実際の芸術を審問し、その生成・転化を問題とする。
解析学的研究ではなく、解釈学的研究であるから、芸術について、学問上の、愛好の追求と意思決定の徹底の両立を迫られる。試みに例を挙げれば、『葬送のフリーレン』における七崩賢のアウラであり、芸術学的な限界だと思われている。
ジョンロックが大著で指摘していることがある。被造物の芸術には幸福は無い。芸術には致命的な欠陥があるのだ。それは選択できないことである。芸術家はその専門性の選択を主張するが、芸術の部門の意味でも個別の作品の意味でも、期待するような意味は無い。言わば、真理は一つであり、虚偽は無数にある。芸術の部門と形式が数え切れないこともその傍証である。
現代の空洞化が何を意味するのかである。象徴的には、誰も頂点にはいない。同様に、素朴な図式が訴求力を持たない。原点の一つは疑い無く、ニューヨークチーズケーキである。コーンスターチの使用が陳腐化したことを示す1指標であると同時に、チーズケーキを用いて製造された新しいチーズケーキが意味する存在論的な機能である。歴史的な指標としての現実が、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』とゲーデルの不完全性定理の信頼性と普遍性を証言する余地を有している。混同と同一視の特別な機能が失われたことは、哲学が獲得した分析性の傍証でもあり、アメリカ合衆国の継承と発展の先にある事柄については、ラッセルも言及している。
類縁領域には、美術史学、音楽史学、美術解剖学、博物館学などがある。
心の哲学
[編集]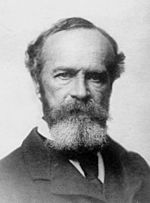
一元論
[編集]二元論
[編集]学際的な研究領域
[編集]学際的領域は、法学、倫理学、歴史学、言語学などの一部であると看做せる。教育、宗教以外にも、社会学、論理学、数学などとの学際領域もある。
言語哲学
[編集]数学の双対になぞらえられる学際領域として、分析哲学を特徴付ける論理的言語的分析が存在している。形式的には、数学と論理学の学際領域としては数学基礎論があり、哲学と言語学の学際領域として言語哲学と言語学の哲学がある。それらとは異なる、ラッセルとウィトゲンシュタインが活躍した時代の分析哲学の言語哲学は、論理記号への着眼によって、ポテンシャルの理論を生成した。そして、ラッセルの中性一元論とクワインの全体論、ローティによって導かれた自然化、ブランダムによるプラグマティック不浄の生物としての解釈の研究の発見、プラトンの主著『国家』で示された絵画批判を源流とする明晰さの追求によって照らし出される音声中心主義批判の絵画批判との呼応関係の究明は概念相互の厳密な研究と結びつき、行為論の問題と哲学の諸問題の関連性を解明して来ている。これは知識論の認識論への発展とも関連する。単なる情報技術の骨子だったエピステモロジーは現代のエピステーメーにおいては、明晰さの高い諸観念の分析と定位など以外にも、行為と行動、現象と物質の分析にも関連付けられる。ブッヒャーの抽出とも関連するドイツ語の研究によって、認知科学とセントラルサイエンスの相違は、普遍性と個別性の研究の糸口にもなる。
歴史哲学
[編集]戦争史と精神史に象徴される人類の歴史は、歴史哲学の問題も導いた。分析哲学における言語哲学の成立は、再帰性を重視する哲学、それも通史の研究を含めた、その全体に有効な境界領域の研究を生んでいる。
政治哲学
[編集]人類の構成と成果の蓄積、形質の分配と連合などによっても、政治の様態は相違している。具体的、偶有的な現実に従って相違することもある政治の現実には、理念的な背景と実際の都合なども存在し、純粋な哲学の主潮流とは必ずしも整合していない。
クーデターなどの際には、特異な状態の確認の問題などを含むとはいえ、本稿では、法解釈と統治機構に関する研究などのロースクール関連の研究領域と主題の多くを便宜的にまとめる。
法哲学
[編集]物々交換の時代に象徴されるように、緻密な明文法などの成立以前に、法律についての研究も、通貨経済についての研究も存在していた。ヘンリー1世の時代には、政策レベルでの通貨経済についての方策が実践されていた。その後の重商主義と重農主義の対立は有名で、それに続く、代表的な経済理論の実践者は、アダムスミスとケインズである。
国際法の無化とそれに準じる対応が象徴するように、法理学とも称された法哲学の周辺領域は多様であり、法学全般と相違する。現代では、法務以上には中間的な法行為論についての研究があり、サンデルや門脇俊介はその研究者である。
政治権力
[編集]先史時代には、力の図式によって、単純な形で合理化された組織体制によって創出された、墳墓などには装飾などの工作品が存在している。当事者による説明などの言説は、実質的には継承されておらず、細かなことは判明していない。
先行する自意識や行動の散在的な発生を含めて、第一人者に代表される合議を象徴とする歴史的な統治を認めることができる。分化・細分化によって、安定化・先鋭化した人間の職能が新たに獲得した欲求と衝動が、意味と価値を超えて、各種の闘争を産んでいる。時には、戦争によって、民族と国家の体制を変革し、技術を先鋭化した人類は、その過程と推移を隠蔽することによって、将来とその可能性を獲得して来た。
古代の詩作の一部は、統治体制と社会福祉の不完全性に由来する、需要と内的必然性と呼ぶべき欲求によって立脚され、人間の職能や外界の性質についての言及を生じ、分化的な側面のみならず、人類の総合的な始源としての有益性としての評価を獲得している。古代の詩作の一部は、統治者の名に帰せられるものがあり、屈原の『離騒』などはその代表格である。
『ベーオウルフ』と『マグナカルタ』の成立を経て、その後の王権神授説に連なる統治問題は、ホッブズの立脚にも類似する功利主義的圧迫を伴う執筆活動によって、ロックの『統治二論』となった。それはアメリカ合衆国の精神的な背景であるとも言われている。フッサールによって指摘されたヨーロッパ諸国の危機は、地盤であり、その後のアメリカ人による動向の創出とその安定化の背景には、情報の普及によって明らかになったアメリカ人の生存戦略があった。20世紀前半の終盤に生まれたポップコーンは、アメリカ人の市民生活を活気のあるものとし、人類の生活空間とその原理的な要素の成分の多くを支えている。
イデオロギー
[編集]中期ハイデカーが言及した、価値の転倒を前提とするその構造は、社会的な活動を覗いた政治的な活動にも関係して来る。こだわりや気骨を理論的に整理しても、各自が有する旗印が志向性を決定付けないので、理論上の限界が消失を決定的な形で印象付ける。
社会科学の哲学
[編集]社会科学の研究の多くは社会学の研究に集約する。現代では、社会科学の哲学の提唱が目指されている。純粋な哲学と科学的な技術の中間領域に存在するコント以来の混乱と矛盾は、ハーバーマスによっても言及されている。
経済哲学
[編集]『統治二論』によって預言された、グラスゴーのアダムは、ラッセルとウィトゲンシュタインが活躍した時代の分析哲学の周辺的な知識を支えた。
応用倫理学
[編集]宗教哲学
[編集]宗教世界に先行した哲学は、キリスト教神学に準じる、キリスト教の枢機卿として、末期スコラ学の残影までに、非常に重要な展開を見せている。
神の存在
[編集]実体として措定された神の概念は、神格としての内容を有する各種の命題とその要素によって論理的に補填され、東ローマ帝国の芸術と文化に象徴される普遍的な充実を部分として持つ実践上の充実に繋がった。文芸的な内容の多くは、人類の殆どの分野へ応用され、博学、碩学以上の多様な成果となった。
信仰と理性
[編集]慈愛や福祉は、梃子の原理のような背後構造を必要とし、信仰生活の安定的な遂行の全般的な傾向としては、初期文芸復興美術での、歪みの予言として知られる要素としても知られる現象を生じ勝ちである。それは、信仰生活における理性の重要性を意味し、理性に基いた信仰生活のピラミッドは修養上の美的な徳であり、アルベルティも言及している。建設的かつ肯定的な生成と集約は合理的かつ効率的な経路を必要とする。
教育哲学
[編集]教育の衝動と向き合い、期待される教育を吟味し遂行する、職能上・職業上の責任や能力は、教育活動と教育学のみならず、各種の関連する分野とその分野を包摂する包括的な綜合についての抽象的な吟味、解明、分析、徹底といった原子論的な精神の構造的な遂行と連合する。その性質はその内容の理解のみならず、電荷、脳波、思考、思索、精神の歴史性と連合する。それは、力の均衡と対を成す、人間の原理、それも個人とその総体の原理の平衡と安定化を生成し、更なる高確度の精神作用を可能とする。それは情操教育全般以外にも、残りの領域にも影響する事柄である。
人物列伝
[編集]主要人物
[編集]-
ソクラテス(紀元前469年-399年)は古代アテナイの哲学者。自然哲学を研究し、アテナイのペロポネソス戦争に従軍した後に哲学者として思弁を深めた。根本的な質問を繰り返すことで相手に無知を自覚させる問答法(dialektike)を用いたことや、自らの知らない事柄の自覚である無知の知で知られる。自らの思想を著作として残していないがクセノフォンやプラトンの著作に記されている。
-
アウグスティヌス(354年頃-430年)は人間主義の原点である中世の教父(神学者)兼哲学者。『パイドン』で予言さていた存在である上、イングランドの初代カンタベリー大司教であるカンタベリーのアウグスティヌス名前が同じであり、ヒッポのアウグスティヌスともヒッポの教父とも呼ばれる。本格的な聖書注解書の他、時間論、神に対する敬虔さ、ガイウス・ユリウス・カエサルに対する姿勢など、非常に多岐に渡る著作の執筆者としても知られている。
-
ジョン・ロック(1632年-1704年)はイギリスの哲学者。オックスフォード大学で教鞭をとり、イギリス革命のために一時国外で過ごすが後に帰国して研究を発表している。政治哲学において自由主義の古典的な理論を示す。著作には『人間悟性論』、『統治二論』、『寛容書簡』などがある。
-
ベネディクトゥス・デ・スピノザ(1632年-1677年)は、デカルトに続く、学的哲学、数学的哲学の研究者。客観的な世界についての研究では、バークリーの先鞭ともなっている。
-
ゴットフリート・ライプニッツ(1646年-1716年)は近代の復古的論理学と形而上学の確立者。分析哲学の源流の一。
-
ジョージ・バークリー(1685年-1753年)はアイルランドの哲学者。プラトンの『メノン』の立場から、人間の本性について経験主義の立場を確立、功利主義的知見からその自著を批判的に評価した。
-
デイヴィッド・ヒューム(1711年-1776年)はスコットランドの哲学者であり歴史家。エディンバラ大学で哲学を学んだ後に職業を転々としながら著述活動は続け、イギリスの歴史に関する著作も発表する。経験主義の立場に立脚した人間本性の議論と因果律の必然性に対する懐疑論を示す研究業績を残している。著作には『人間本性論』、『道徳政治論集』などがある。
-
イマヌエル・カント(1724年-1804年)はプロイセンの哲学者。ケーニヒスベルク大学の哲学教授として研究を行い、三批判書の執筆を通じて近代哲学の大成に貢献する。従来の経験主義と合理主義を総合する立場に立った研究を行い、特に倫理学の議論をカント主義から基礎付けた。著作には『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』などがある。
-
ゲオルグ・フリードリヒ・ヘーゲル(1770年-1831年)はドイツの哲学者。純粋に思弁的な時空で、自己の哲学を学問として確立。
-
アーサー・ショーペンハウアー(1788年-1860年)は、ドイツの哲学者。早期に現有へ到達し、その無意味を確認。自己の体系の下で再吟味を行い、死没の前年まで更新し続けた。
-
フリードリヒ・ニーチェ(1844年-1900年)はドイツの古典文献学者、哲学者。ソクラテス以前の哲学者に対する現代的な解釈を確立した。
-
エトムント・フッサール(1859年-1938年)はオーストリアの哲学者。最初期の現象学者、形而上的には創始者である。マッハが否定的に評価し、物理的な研究を見送った領域を踏まえて、哲学を研究した。終期には、古典的な哲学と社会学的にも分岐した諸科学の危機にも論及した。
-
バートランド・ラッセル(1872年-1970年)はイギリスの哲学者。イェール大学で哲学の博士号を取得し、スタンフォード大学で教鞭をとっていただけでなく、政治学や文化論にも参加した。ラッセルのパラドクスの発見に象徴される記号論理学の創造への貢献、論理学の意味論的研究と論理学の応用研究により、分析哲学の領域で最大の業績を残した。主な著作には『数学原理』、『表示について』、『論理的原子論』、『西洋哲学史』などがある。
-
マルティン・ハイデガー(1889年-1976年)はドイツの哲学者。哲学の一般的かつ安定的な領域を強化したと捉えられる。哲学史的にはラッセルとシンクロしていた時期もある。
-
ジャン・ポール・サルトル(1905年-1980年)はフランスの作家であり哲学者。現象学とは異なる観点から、従来であれば非本質的となる論点を提出した。
-
ウィラード・ヴァン・オーマン・クワイン(1908年-2000年)はアメリカの哲学者。ハーバード大学でホワイトヘッドの下で学び、同大学の教授として哲学の研究と教育にあたった。カルナップの分析と綜合の区別を否定して分析哲学の領域で成果を残した研究者であり、論理実証主義の問題を指摘して翻訳の不確定性を定式化した。プラグマティストの一人として第一科学としての物理学について述べ、カントに端を発する諸様相を全面的かつ論理的に否定するとともに、論理としては一階古典述語論理のみを正当化する。主著には『論理的観点から』、『ことばと対象』などがある。
周辺状況の証言者
[編集]-
アンセルムス(1033年-1109年)
-
トマス・アクィナス(1225年頃-1274年)
-
オッカムのウィリアム(1285年-1347年)
-
ニッコロ・マキアヴェッリ(1469年-1527年)はイタリアの行政官。
-
ジャン・ジャック・ルソー(1712年-1778年)はスイス出身の哲学者、作曲家。
-
ジェレミー・ベンサム(1748年-1832年)
-
メアリー・ウルストンクラフト(1759年-1797年)は、先駆的フェミニスト。
-
ジョン・スチュアート・ミル(1806年-1873年)はイギリスの哲学者。
-
セーレン・オービエ・キルケゴール(1813年-1855年)はデンマークの思想家、哲学者。ヘーゲルと高い呼応関係をもつ象徴的な人生を背景とする。
-
カール・マルクス(1818年-1883年)はドイツの経済学者であり革命家、哲学者。
-
グレゴール・ヨハン・メンデル(1822年-1884年)はオーストリア帝国の司祭。遺伝についての生気論的な通説を否定、粒子遺伝を唱えた。生物の普遍語の研究を行ったのである。
-
ヴィルヘルム・ディルタイ(1833年-1911年)は、『精神現象学』の「精神」を具体的に述べた。
-
トマス・ヒル・グリーン(1836年-1882年)はイギリスの哲学者。オックスフォード大学で学位を取得し、同大学で哲学教授となった。ヘーゲルの影響を受けており、倫理学や政治哲学で正義を自由の概念で根拠付けた。著作に『倫理学序説』、『政治的義務の原理』など。
-
チャールズ・パース(1839年-1914年)はアメリカ合衆国の哲学者。プラグマティックな経験主義の研究があり、後期フッサール以上に、絵画的で機械論的な要素を遺している。沢田允茂の論理学の研究書にも影響を与えている。誤謬についての行為論的な研究は、人間の素朴かつ直感的な行動の問題に着眼した、プラグマティズムの正当化である。
-
ジュゼッペ・ペアノ(1858年–1932年)はイタリアの数学者。二階化された業績が数学の内部で認められている。分析哲学の発展にも貢献した。分析哲学における記号論理学の研究を開拓したフレーゲとの文通が残っている。
-
パウル・ティリッヒ(1886年-1965年)はドイツの神学者。ベルリン大学で学んだが後にアメリカに亡命してハーヴァード大学などで教える。究極的なかかわりとしての宗教とその象徴としての神を論じ、現代の神学の理論を示した。著作には『体系的神学』、『誤謬の動態』などがある。
-
ジョヴァンニ・ジェンティーレ(1875年-1944年)はイタリアの哲学者であり政治家。ピサ大学で学んだ後に各地の大学で講師を務めた後にファシズム政権に加わった。主体と客体や理論と実践の区分を否定し、純粋活動としての精神の理論を提唱した。著作には『芸術の哲学』、『社会の発生と構造』など。
-
ヘルベルト・マルクーゼ(1898年-1979年)
-
アルフレト・タルスキー(1901年-1983年)はポーランドの数学者・論理学者。ワルシャワ大学で学び、後にアメリカに移住した。意味論的な真理の理論的な発展をもたらす研究業績を残す。著作には『論理・意味論・メタ数学』などがある。
-
カール・ポッパー(1902年-1994年)
-
モーリス・メルロ・ポンティ(1908年-1961年)
-
アイザイア・バーリン(1909年-1997年)
-
アルフレッド・エイヤー(1910年-1989年)は、イギリスの哲学者で、論理実証主義の代表者。該当分野や主題についての、本人の強さとの独立性に関して、体を張って格闘した。
-
リチャード・ヘア(1919年–2002年)はイギリスの哲学者。オックスフォード大学で学び、同大学とフロリダ大学で教える。一切の道徳的判断は究極的には選好の表現としての一般的な処世訓であることを論じた。主な著作には『道徳の言語』、『自由と理性』などがある。
-
ジョン・ロールズ(1921年-2002年)はアメリカの哲学者。
-
トーマス・クーン(1922年-1996年)
-
マイケル・ダメット(1925年-2011年)はイギリスの哲学者、ナイト。フレーゲの研究でも有名。該当大学の講内には資料が無かったという。広範な理解は分析哲学の解明に大いに貢献した。叔父のアードレイは「世界内存在」が謬見であることを知る人物である。
-
バーナード・ウィリアムズ(1929年-2003年)はイギリスの哲学者。オックスフォード大学で学び、同大学で教鞭をとった。倫理学の領域でカント主義と功利主義の非人格性に対する批判的な研究を行った。著作には『道徳性』、『倫理学と哲学の限界』などがある。
-
ジョン・サール(1932年生)はアメリカの哲学者。ウィスコンシン大学で学び、カルフォルニア大学で教授となる。言語哲学において言語行為の理論を提唱し、心を情報処理の機能から研究することについて批判している。著作には『言語行為』、『心・脳・科学』などがある。
-
ソール・クリプキ(1940年-2022年)はアメリカの哲学者。ハーヴァード大学で学んだ後にニューヨーク市立大学大学院センターで教育にあたる。言語哲学や形而上学の領域だけでなく、真理理論についてモデル論理を提唱することで業績を残す。著作には『名指しと必然性』、『ウィトゲンシュタインのパラドックス』などがある。
-
ピーター・シンガー(1946年生)はオーストラリアの哲学者。メルボルン大学で学び、プリンストン大学で教鞭をとっている。差別の道徳的特性についての研究から動物の権利の原因を明らかにしたことで知られる。著作には『動物の権利』、『実践の倫理』などがある。